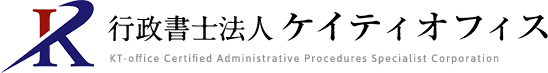労働保険事務組合ケイティオフィス
事業主様に代わり労働保険事務を代行します
労働保険事務組合ケイティオフィスでは、労働保険の事務手続きを委託していただけるだけでなく、事業主・役員であっても「特別加入」という制度で労災保険に加入することができます。
従業員を雇用されている事業主の皆様は、労働保険(労災保険及び雇用保険)を成立する必要があります。
労働保険事務組合とは
厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険の手続きを事業主の委託を受けて、事務代行をする団体です。
-
事務負担の大幅な軽減
従業員様が入退社された際の雇用保険手続きをスピーディに行います。
-
保険料を年3回に分割納付
保険料の額に関わらず保険料納付を3回に分割できます。保険料が高額の場合には資金繰りが楽になり、また分割手数料も発生しません。
-
労災特別加入に対応
事業主・事業主の家族従事者・法人役員が労災保険に特別加入できます。
-
従業員雇用が初めてでも安心
初めて従業員様を雇入れされた際の労働保険関係の手続きを行います。
-
行政書士事務所が併設
建設業許可等の許認可について相談できます。
-
給与計算・経理記帳
併設している行政書士事務所が給与計算や経理記帳を受託することができます。
-
建設キャリアアップシステムの相談ができる
認定登録機関建設キャリアアップ登録センターが併設しています。
-
電子申請に対応
電子申請で行うのでスピーディーに手続きを行います。
本来は労災保険は、労働者の業務または通勤 による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の「事業主」「事業主の家族従事者」「法人役員」でも、その業務の実情、災害の 発生状況などからみて、特に労働者に準じて保 護することが適当であると認められる一定の方 には特別に任意加入を認めています。
補償範囲:業務災害・通勤災害に起因する治療費、休業補償、障害補償給付 等
-
常時使用する労働者が下記表内
業種 常時使用労働者数 金融・保険・不動産・小売業 50人以下 卸売業・サービス業 100人以下 上記以外の業種 300人以下 - 上記の範囲内であれば、パートタイマー・アルバイトを含む総人数で判定されます。
-
労働保険事務組合ケイテイオフィスの会員事業所
-
従業員を雇用していること(年間100日以上)
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務(従業員の雇入・退職の時)
- 概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務(年度更新)
- 保険関係成立届の申請、雇用保険事業所設置届提出等に関する事務(新規適用)
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- その他労働保険についての申請、届出に関する事務(名称・所在地の変更等)
- 印紙保険料に関する事項は除きます。
| 常用労働者数 | 委託月額手数料(税込) |
|---|---|
| 1~4名 | 1,430円 |
| 5~15名 | 1,760円 |
| 16~30名 | 2,530円 |
| 31~50名 | 3,520円 |
| 51~70名 | 4,510円 |
| 71~100名 | 7,260円 |
| 101~200名 | 9,900円 |
| 201~300名 | 14,300円 |
- 別途、月会費2,000円(不課税)が必要となります。
給付基礎日額
給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)等給付などの給付額を算定する基礎と なるもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。給付基礎日額が低い場合は、 保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)等給付などの給付額も少なくなりま すので、十分ご留意の上、適正な額を申請してください。
- 印紙保険料に関する事項は除きます。
保険料
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定めら れた保険料率を乗じたものになります。
年間保険料=保険料算定基礎額※×保険料率
(例)建設事業(既設建築物設備工事業)の場合 保険料率 12/1000
- 特別加入者各員の保険料算定基礎額を合計した額に1円未満の端数が生じるときは、端数切り捨てとなります。
| 給付基礎日額 (A) |
保険料算定基礎額(B) A×365日=Bに変更 |
年間保険料 |
|---|---|---|
| 25,000円 | 9,125,000円 | 109,500円 |
| 24,000円 | 8,760,000円 | 105,120円 |
| 22,000円 | 8,030,000円 | 96,360円 |
| 20,000円 | 7,300,000円 | 87,600円 |
| 18,000円 | 6,570,000円 | 78,840円 |
| 16,000円 | 5,840,000円 | 70,080円 |
| 14,000円 | 5,110,000円 | 61,320円 |
| 12,000円 | 4,380,000円 | 52,560円 |
| 10,000円 | 3,650,000円 | 43,800円 |
| 9,000円 | 3,285,000円 | 39,420円 |
| 8,000円 | 2,920,000円 | 35,040円 |
| 7,000円 | 2,555,000円 | 30,660円 |
| 6,000円 | 2,190,000円 | 26,280円 |
| 5,000円 | 1,825,000円 | 21,900円 |
| 4,000円 | 1,460,000円 | 17,520円 |
| 3,500円 | 1,277,500円 | 15,330円 |
保険給付・特別支給金の種類
特別加入者が業務または通勤により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。
| 保険給付の種類 ※1 |
支給事由 | 給付内容 | 特別給付金 |
具体的な例 (給付基礎日額 1万円の場合) |
|
業務/複数事業の業務/通勤による傷病について、病院等で治療する場合 | 労災病院または労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。また、労災病院または労災指定病院等以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。 ※2 |
特別支給金はありません。 | (給付基礎日額とは関係なく)必要な治療が無料で受けられます。 |
|
業務/複数事業の業務/通勤による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合 ※3 |
休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 | 休業特別支給金休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額を支給。 | 20日間休業した場合 ①休業(補償)等給付 1万円×60%×(20日-3日)=10万2千円 ②休業特別支給金 1万円×20%×(20日-3日)=3万4千円 |
|
〔障害(補償)等年金〕 業務/複数事業の業務/通勤による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合 〔障害(補償)等一時金〕業務/複数事業の業務/通勤による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合 |
〔障害(補償)等年金の場合〕 第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は給付基礎日額の131日分が支給されます。 〔障害(補償)等一時金の場合〕 第8級は給付基礎日額の503日分~第14級は給付基礎日額の56日分が支給されます。 |
障害特別支給金第1級342万円~第14級8万円を一時金として支給。 |
(第1級の場合) ①障害(補償)等年金 1万円×313日=313万円 ②障害特別支給金(一時金) 342万円 |
|
業務/複数事業の業務/通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において ①傷病が治っていないこと、②傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること、のいずれにも該当する場合 |
第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は給付基礎日額の277日分、第3級は給付基礎日額の245日分が支給されます。 |
傷病特別支給金 第1級は114万円 第2級は107万円 第3級は100万円 を一時金として支給。 |
(第1級の場合) ①傷病(補償)等年金 1万円×313日=313万円 ②傷病特別支給金(一時金)114万円 |
|
〔遺族(補償) 等年金〕 業務/複数事業の業務/通勤により死亡した場合(年金額は遺族の人数に応じて異なります) 〔遺族(補償)等一時金〕 ①遺族(補償)等年金の受給資格をもつ遺族がいない場合 ②遺族(補償)等年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金の受給資格をもつ方がいない場合で、すでに支給さ れた年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合 |
〔遺族(補償)等年金の場合〕 遺族の人数によって支給される額が異なります。 (遺族1人の場合) 給付基礎日額の153日分または175日分 ※4 (遺族2人の場合) 給付基礎日額の201日分 (遺族3人の場合) 給付基礎日額の223日分 (遺族4人以上の場合) 給付基礎日額の245日分 〔遺族(補償)等一時金の場合〕 左欄の①の場合 給付基礎日額の1000日分 左欄の②の場合 給付基礎日額の1000日分からすでに支給した年金の合計額を差し引いた額 |
遺族特別支給金 遺族の人数にかかわらず300万円を一時金として支給 |
〔遺族(補償)等年金で遺族が4人の場合〕 ①遺族(補償)等年金 1万円×245日=245万円 ②遺族特別支給金(一時金) 300万円 〔遺族(補償)等一時金支給事由 ①の場合〕 ①遺族(補償)等一時金 1万円×1000日=1000万円 ②遺族特別支給金(一時金)300万円 |
|
業務/複数事業の業務/通勤により死亡した方の葬祭を行う場合 | 31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。 | 特別支給金はありません。 |
①31万5千円+(1万円×30日)=61万5千円 ②1万円×60日=60万円 よって、高い額の①が支払われます。 |
|
業務/複数事業の業務/通勤により、障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 |
介護の費用として支出した額(上限額があります)が支給されます。親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が最低保障額を下回る場合は一律にその最低保障額が支給されます。 上限額および最低保障額は、常時介護と随時介護の場合で異なります。 |
特別支給金はありません。 |
〔常時介護を要する者〕 上限額 177,950円 最低保障額 81,290円 〔随時介護を要する者〕 上限額 88,980円 最低保障額 40,600円 ※5 |
- 「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、中段は複数業務要因災害、下段は通勤災害に対して支給される保険給付の名称です。
- 原則、給付の範囲は健康保険に準拠しています。
- 休業(補償)等給付については、特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能であることが必要となっています。全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいいます。
- 遺族(補償)等年金の受給資格者である遺族が1人であり、55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合には、給付基礎日額の175日分が支給されます。
- 表中の金額は、令和6年4月1日現在のものです。
- 船員保険の適用を受ける船員の方が、労災保険給付を受けたときには、船員保険の上乗せ給付がある保険給付について、全国健康保険協会に対し、上乗せ給付の請求を行うことができます。
- その他については下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
01
まずはお電話でお問い合わせください。制度等のご説明をさせていただきます。
御予約の上、当組合にお越しいただきご説明させていただくことも可能です。
組合の加入・委託のお申し込み
02必要書類をご提出の上、お申し込みいただきます。
委託開始
03当事務組合が労働局・労働基準監督署・ハローワークに手続きを行います。
関係書類の送付
04手続き後、労働保険関係書類をお送りします。その際に労働保険番号もお知らせします。
従業員様の入退社手続き
05従業員様が入退社されましたら当事務組合に連絡お願いします。労働保険関係の手続きを行います。
労働保険年度更新
06毎年1回行う必要がある労働保険年度更新(概算保険料・確定保険料等の申告)を行いますので、給与関係の書類の提出をお願いします。
- 従業員がいない一人親方ですが労災特別加入できますか?
- 年間100日以上、従業員を雇用していない一人親方は当事務組合では労災特別加入ができません。
- 労災特別加入は事務組合に委託しなくても自分で加入手続きできますか?
- 国が定めた制度上、労働保険事務組合に委託する必要があります。
- パート・アルバイトのみを雇用していますが、労災保険の手続きが必要ですか?
- パート・アルバイトに関わらず、労働者を1人でも雇っている場合は労災保険の成立手続が必要です。
- 労働保険とは何でしょうか?
- 労働保険とは仕事中や通勤が原因で負傷や死亡した場合を保護するための「労災保険」と、失業した場合や教育訓練を受けた場合に給付を受けるための「雇用保険」の総称です。
- 労働保険料の負担はどのようになっていますか?
-
労災保険料…全額事業主負担
雇用保険料…事業主と労働者双方で負担
※負担率はお問い合わせください。 - 事業主と同居している親族は、労働保険に加入することは出来ますか?
-
同居の親族は、労働保険上の「労働者」に該当しませんが、同居の親族であっても、常時同居親族以外の労働者を使用する事業において、下記の条件を満たす場合に「労働者」に該当し、労働保険に加入することが出来ます。
- 業務を行うにつき事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
-
就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
- 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期等の就業規則が他の労働者と同様であることが条件です。